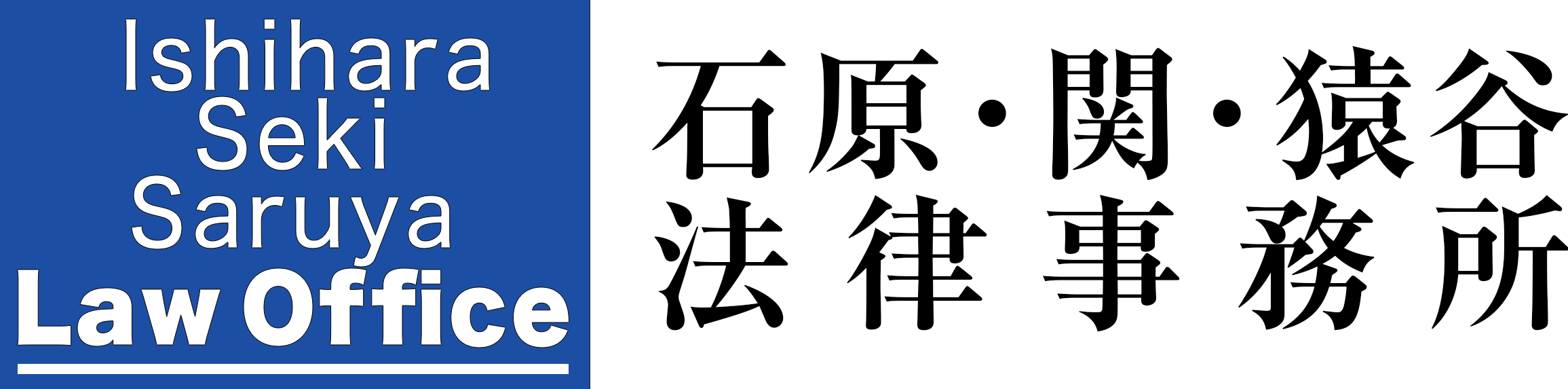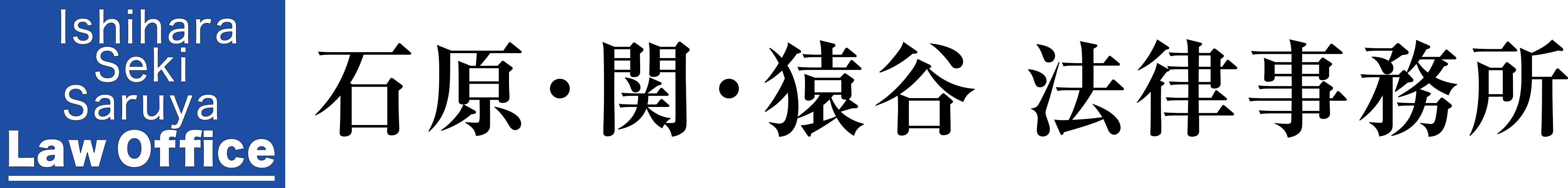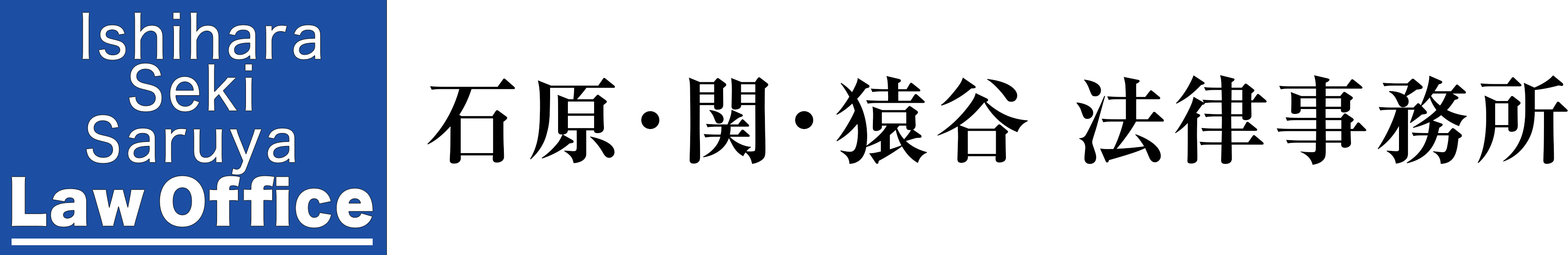前橋市は、12月議会で、前橋市暴排条例を制定しました。この条例は平成24年4月1日から施行になります。
12月13日付け朝日新聞によれば、東京都公安委員会は12日、業者と都内に住む指定暴力団幹部に、東京都暴排条例を適用し勧告をしたようです。都暴排条例は10月に施行されました。 事案は、観葉植物リース業を営む暴力団員が、10月下旬、埼玉県内の造園業者に都内の飲食店など数十店舗で、リース代を徴収させたり、観葉植物を交換させたりしたというものです。
去る9月24日(土)、群馬弁護士会の弁護士4名で、いわき市にある仮設住宅を訪問しました。 相談会場として用意して頂いた集会所で被災者から法律相談を受けましたが、相談者全員が東電への請求書の記載方法などに関する相談でした。 「まるっきり分からない!」ご年配の女性が訴えていました。記載の内容や方法が分からず困っている様子でした。東電からは200頁を越える書類が避難者に送られて来ました。これを読んで請求書を書くことは至難の業。そう感じたとしても何の不思議もありません。
9月5日(月)、神戸市で日弁連主催の標記協議会があり出席してきました。 協議会では、被災地弁護士会の支援活動、県内避難者への支援活動や被災者支援の仕組みなどについて報告があった後、広域避難者への支援体制などについて意見交換が行われました。
9月1日付けの新聞各紙によれば、法曹養成制度を見直すため政府が設置した「法曹の養成に関するフォーラム」は、8月31日の第5回会議で、第1次取りまとめを行ったようです。 法曹養成フォーラムは、平成22年11月24日、「裁判所法の改正に関する件」が衆議院法務委員会で決議されたことに受けて、平成23年5月13日、内閣官房長官ら関係する大臣の申し合わせにより開催が決まったのですが、司法制度改革の理念を踏まえ次の事項を検討することを使命とするとしています。 ①個々の司法修習修了者の経済的な状況等を勘案した措置の在り方 ②法曹養成に関する制度の在り方 今回の第1次取りまとめでは、①について司法修習生への経済的支援の在り方としては「貸与制を基本とした上で、個々の司法修習修了者の経済的な状況等を勘案した措置を検討すべきであるとの意見が大勢を占めた」としています。また、②については引き続き検討するとしています。 このようなフォーラムの第1次取りまとめに対しては、早速、反対意見の声明が出されています。 司法修習生に対する給与の支給継続を求める市民連絡会は「今日のわが国法曹養成にかかる最大の問題は、裁判官や検察官・弁護士になるには、あまりにお金がかかりすぎる仕組みになっていることにある」とし、給費制を廃止すれば一般市民にとって法曹の道はさらに遠くなり、ひいてはわが国法曹の質の低下につながることは明らかである、給費制の存廃は法曹養成にかかる制度全体の見直しの中で結論を見い出すべきだと主張します。
先日、司法修習生と一緒に国立療養所栗生楽泉園を訪問しました。楽泉園は群馬県吾妻郡草津町にあるハンセン病療養所です。 今更ですがハンセン病に関する歴史や裁判の話をお聞きし、偏見や差別のもたらす深刻な結果を学ぶことが出来ました。 ハンセン病はノルウェーのハンセン医師が1873年に発見した「らい菌」による感染症ですが、感染力は弱くたとえ感染しても発病することはまれです。すぐれた治療薬もあります。 ハンセン病はかつては「らい病」と呼ばれ体の末梢神経が麻痺したり皮膚に発疹が出ることなどが特徴で、病気が進行すると顔や手足が変形することから、患者は差別の対象になりやすかったようです。 わが国ではハンセン病対策として誤った強制隔離政策が長く続いてしまいました。そのことが偏見や差別が現在でも根強く残っている原因のひとつとされています(厚生労働省発行「わたしたちにできること~ハンセン病を知り、偏見や差別をなくそう~」)。
県内避難者や市民が約120名参加し、約30名の群馬弁護士会の会員が対応しました。説明会の様子が見られます。
群馬弁護士会による説明会が初めて開催されます。 日 時:8月20日(土)午後2時~4時 会 場:群馬県社会福祉総合センター 参加費:無料 定 員:300名 群馬弁護士会(電話027-233-4804)では参加する場合には予約するようお願いしています。
群馬弁護士会の会員が福島県からの避難者の避難所を訪問し、いわゆる二重ローン問題で苦しむ被災者を支援するため署名活動を行いました。
7月10日(日)、福島県いわき市において、福島県弁護士会による原発事故に基づく損害賠償請求の説明会があり、お手伝いに行ってきました。 説明会では、福島県原子力災害被災者・記録ノート(いわゆる被災者ノート)が無料配布され、補償問題に備え記録をつけることが説明されていました。