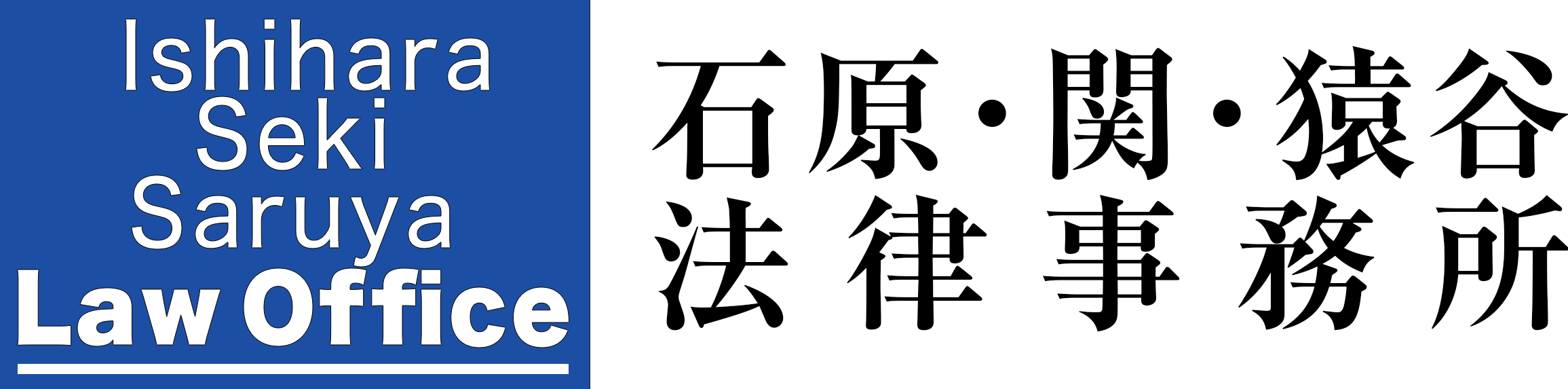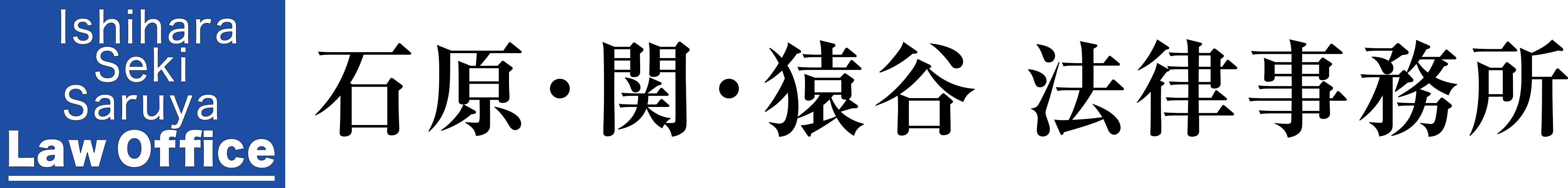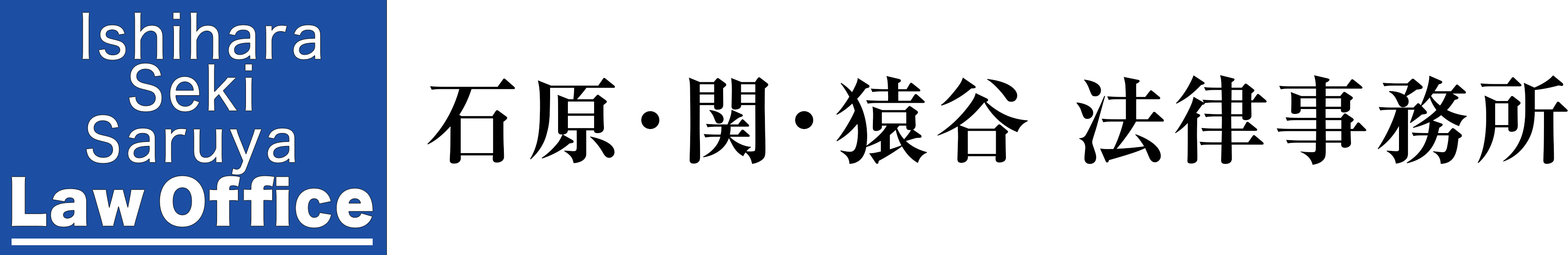群馬県公安委員会は、1月15日及び16日、指定暴力団稲川会系の組長(59)及び県内会社役員(51)を含む6名に対し、暴力団員等への利益供与等を禁止した県暴排条例に基づいて、同様の行為をしないよう勧告したとのことです。1月17日付けの上毛、読売、朝日などの各紙に掲載されています。 事案は、昨年7月7日、組長が県内の飲食店で会合を主催し、参加者約20名から計約20万円を受け取ったとのことです。上記6名は1人あたり8000円から1万円を渡したという。 平成23年4月1日から施行された群馬県暴排条例は、事業者が暴力団員等に対し金品等を供与することを禁じています(第17条)。 そして、①これに違反した疑いがある者に対しては、違反の事実を明らかにするために説明又は資料の提出を求めることができ(22条)、②違反行為があった場合には、違反者に対して必要な勧告をすることができ(23条)、③正当な理由なく説明若しくは資料提出を拒み、又は勧告に従わないときは、その旨を公表できる(24条)、とされています。 公表の方法は、群馬県報への登載及びインターネットの利用によって行われます。公表される内容は、氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者氏名並びに主たる事務所の所在地)並びに公表の原因となる事実です(施行規則10条)。
新年明けましておめでとうございます。
10月22日(土)、高崎経済大学において、日弁連と群馬弁護士会の主催で、貧困問題についての講演がありました。 小生、参加してみました。 基調報告では、わが国の現状として、平成7年以降生活保護受給者数が急速に増加していること、平成23年6月の受給者数は204万1592人に達したこと等が報告されました。過去最多であった1951年度の204万6646人に迫る勢いとのことです。 報告者は、その主な原因として次のことを指摘しています。 ①非正規労働者の増加 ②高止まりの失業率 ③地方経済の崩壊 ④最低賃金制度が機能していないこと ⑤社会保障制度の大幅な後退 基調講演では、スウェーデンの社会保障政策について興味深い講演がありました。スウェーデンでは税負担率が平均で46%と非常に高い水準にありますが、他方で、税金の使い道の透明性が確保されるなど市民が税金について納得できる仕組みができているようです。
6月末、仕事で新潟市に行った際、タクシーの運転手さんに薦められて行ってみました。水道タンクのうえに展望台があるという珍しい施設です。
26日の上毛新聞に、群馬県公安委員会が、25日、暴力団対策法に基づき、みかじめ料を要求しないよう再発防止命令を出したとという記事が掲載されています。 事案は、指定暴力団幹部が、今年1月と2月に、前橋市内のスナック経営者と飲食店経営者に、それぞれ「みかじめ料」を要求したというものです。これに対し、県公安委員会がみかじめ料要求を禁止したということです。 ところで「みかじめ料」って何? 暴力団対策法9条は指定暴力団員による様々な暴力的要求行為を禁止していますが、そのひとつに「みかじめ料要求行為」の禁止(同条4号)があります。 同条4号によれば、「みかじめ料」とは「縄張内で営業を営む者に対し、名目のいかんをを問わず、その営業を営むことを容認する対償として」の金品等のことを言います。 このような金品等を要求することが「みかじめ料要求行為」です。暴力団対策法9条はこのような「みかじめ料要求行為」を禁止しています。そして、県公安委員会は当該指定暴力団員に対し、みかじめ料要求行為などの暴力的要求行為の中止、又は中止を確保するための必要な事項を命じるという行政処分を下すことができます(同法11条)。 今回の事案では、当該指定暴力団幹部が、「反復して」当該暴力的要求行為をするおそれがあると認められたため、「再発防止命令」が出されたようです。
4月24日の上毛新聞によれば、23日、群馬県草津町で暴力団からのみかじめ料などの不当要求を団結して拒否するための「草津湯の町みかじめ料等縁切り同盟」が結成され、町役場で関係者130名が出席して結成式が行われました。
群馬県内で初めての縁切り同盟結成であり、県内の暴排活動において大変有意義な出来事です。
明けましておめでとうございます。 今年こそは平穏な一年であってほしいと思います。 さて、東京新聞などの新聞各紙に、群馬弁護士会が県内に避難している人を対象にアンケート調査を実施していることが報道されています。 このアンケートは県内避難者の生活費増加分を調査するために行われているものです。県内避難者の生活費増加分の標準値を算出して原発被害者への賠償手続きが効率的に行なわれることを目的として実施されています。