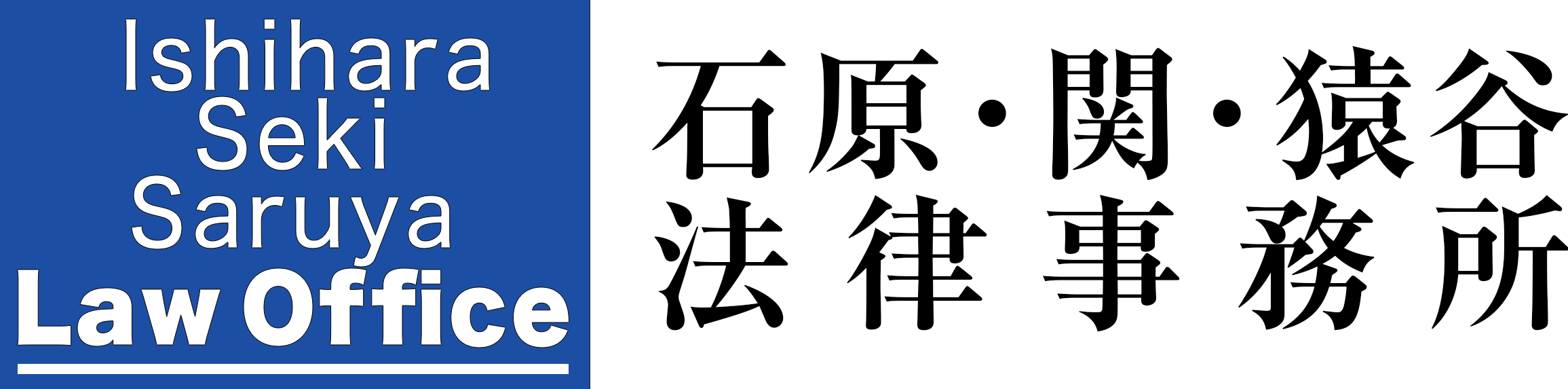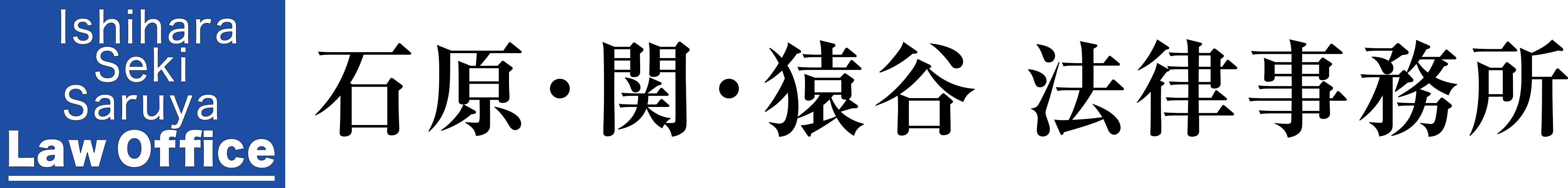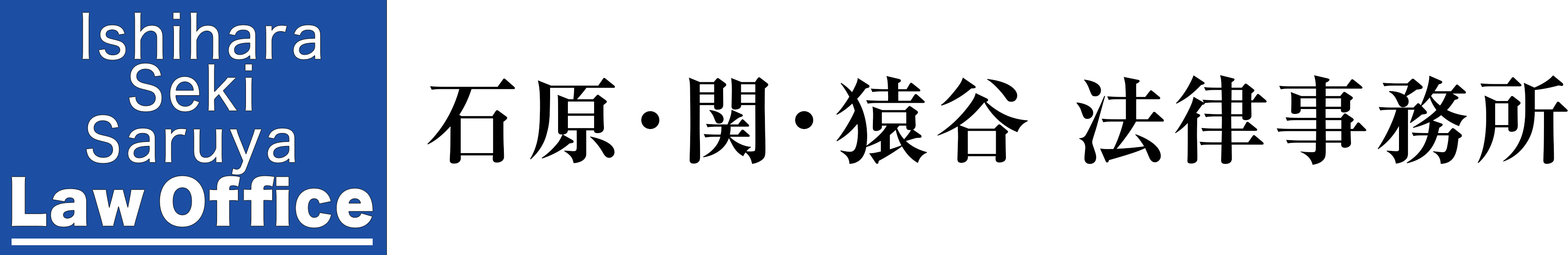震災の影響により、電力の供給が不足することから、東京電力は計画停電を実施すると発表し、本日、群馬県の一部などで実施されました。 電気や石油などのエネルギーの供給や消費に対する認識を改める必要があるとつくづく感じました。当事務所でも、ささやかですが室内や屋外の電灯の灯火時間や暖房の温度を見直すなど節電の取り組みを始めました。
被災した地域の皆様には心からお見舞い申し上げます。 弁護士会も、被災者の救援のため何ができるか速やかに検討し逐次実行しなければならないと思います。 *追記 去る16日、群馬弁護士会でも災害対策委員会が開催され、震災への対応が協議されました。弁護士としてできることは限られていますが、群馬弁護士会では、中越地震の際、新潟に弁護士を派遣して災害被害者の法律相談にあたった経験があります。 近い将来実施されるであろう災害被害者の法律相談に備えて、地震等の災害に関する法律問題について研修すること等が必要だと感じました。 研修のための文献のひとつとして、「Q&A災害時の法律実務ハンドブック」(新日本法規)があります。関東弁護士会連合会に所属する弁護士が平成18年に共同執筆で作成したものです。とても参考になる文献ですが、津波や原子力災害についても詳細な記述がほしいと感じました。 *追記 文献については日弁連災害復興支援委員会編「災害対策マニュアル」(商事法務)もあります。被災者の法律相談を受ける弁護士にも極めて参考になる本です。
3月1日(火)、地元選出の国会議員や秘書の方々と弁護士との勉強会に参加しました。 群馬弁護士会の関弁護士が「政治活動の自由とその規制」について講演した後、弁護士会が取り組んでいる政治的課題について、ざっくばらんな意見交換会がありました。 ここでも、①司法修習生の給費制、②取り調べの可視化などが議論されました。 国会議員側から、①について法曹養成制度全体のなかでどのように位置づけられるのかという指摘があり、同感でした。 ②については、日弁連の資料によれば、現在までに全国で5の府県、145の市町村の各議会において取り調べ可視化を求める意見書が採択されているとのことです。
2月26日(土)午後、群馬弁護士会の総会がありました。 今日の弁護士会が抱える様々な問題が報告され審議されました。また、平成23年度の弁護士会役員が紹介され記者会見がありました。 我が事務所からは、関弁護士が副会長として平成23年度群馬弁護士会の新役員に選任されました。活躍を大いに期待したいと思います。 ところで、新会長に決まった小渕弁護士はマスコミに対し、①取り調べ可視化、②裁判員裁判、③司法修習生給費制、④法曹養成制度、⑤円滑な会運営などについて、抱負を語ったと報道されています。 いずれも難しい問題ですが、私たち市民生活に関わることであり、ひとつひとつ丁寧に対応することが求めれていると感じました。 例えば、取り調べの可視化問題は、足利事件の再審裁判、厚生労働省局長事件の裁判がきっかけで社会問題化し政府内でも検討が始まりました。取調過程を録音・録画して可視化することは誤審、誤捜査をなくすため是非取り組むべき課題ですが、(ア)可視化によって誤審を防止することがどの程度できるか、(イ)可視化によって適正な捜査が阻害することがないかなど、様々な観点から検討しなければならないテーマであると考えます。 そのうえで、どのような内容の可視化をどの程度実施することが適当かを判断すべきだと考えます。
本年1月から私共の事務所に笠本秀一弁護士が加わりました。笠本弁護士は弁護士2年目の新人弁護士です。宜しくお願い申し上げます。笠本弁護士の入所により事務所の弁護士は総勢6名になりました。 ところで、現在、司法研修所を卒業する司法修習生の人数は約2000人ですが、弁護士を希望する修習生のなかには法律事務所に就職できない人が出てきているようです。 法曹としての知識や能力の取得は生涯続きますが、少なくとも司法研修所での研修だけで十分とは到底言えません。その観点から、司法研修所卒業後の実務訓練、オン・ザ・ジョブ・トレーニング(OJT)が重要であると言われています。 法律事務所に就職できない新人弁護士のなかには、OJTによる資質向上の機会が制限されている弁護士がいるということになります。 弁護士は市民の大切な権利や財産を守ることが重要な仕事のひとつです。従って、市民の権利や財産を保護するという観点からすれば、新人弁護士の研修や資質向上の機会は十分保証されるべきでしょう。このような機会が制限されることのないようにすべきです。 そのためには、司法研修所を卒業する司法修習生の多くが就職できるような法曹養成の制度設計がなされなければならないと思います。 *追記 「そくどく」という言葉をお聞きになったことはありませんか。「速読」ではありません。「即独」と書きます。弁護士のことなのですが、既存の法律事務所に就職せず弁護士登録と同時に事務所を構える弁護士のことを「即独弁護士」と表現することがあります。 最近即独した弁護士の報告を読みましたが(関弁連発行・ひまわり14号)、身近に指導する弁護士がいないこと、扱う事件の数や種類が少ないことなどで苦労したことが報告されています。 弁護士の自助努力、先輩弁護士からの事件の紹介や「共同受任」などによってこういった問題を克服しているようですが、そのような自助や共助は何時まで続けることができるのでしょうか。報告の中には「即独してやっていくことは以前ほど簡単なことではなくなってきたと思います」という指摘があります。
新年あけましておめでとうございます。 群馬県の元日はニューイヤー駅伝で始まります。午前9時10分にスタートし、今まさに実業団の選手達が上州路を駆けているところです。
新第64期司法修習生の実務修習が開始しました。 本日、前橋地裁にて修習開始式が行われ来年9月までの実務修習が始まりました。前橋地裁で実務修習する司法修習生は27名です。 今回の修習生については「給費制」が廃止になるか否かが議論されましたが、11月26日、司法修習生に対する貸与制の施行を1年間延期する法律が国会で可決・即日公布され、とりあえず1年間の期限付きで給費制が継続されるという結論になりました。 市民の権利を守る法律家を市民の負担で養成することは十分合理性があることだと思います。それが給費制存続を求める理由のひとつです。
群馬県は、9月の県議会において群馬県暴力団排除条例を制定し、10月28日、これを公布しました。
来年4月1日から施行されます。
日差しの強い日が続きます。 今年は外出するとき日傘が手放せません。